���j�P���@����ƃW�F���_�[�i�����搶�j �@�@�@�@�@2007/01/19
DICOM M1 �H�c �h��
Sachiko Ide(��o�ˎq)
Women�fs language as a group identity marker in Japanese
�P�DIntroduction
![]() ��ʓI�ɁA���{��̏�����͂�蒚�J�ł���ƌ����Ă���B�i��j�h��A�I����
��ʓI�ɁA���{��̏�����͂�蒚�J�ł���ƌ����Ă���B�i��j�h��A�I����
![]() ��ʘ_�ɔ��_����ŋ߂̌���
��ʘ_�ɔ��_����ŋ߂̌���
�@Ide, Hori, Kawasaki, Ikuta& Haga(1996)
�@�@�@�����̒��J�Ȍ��t�����́A�Љ�I�n�ʂ��������̈Ⴂ�ɂ��B
![]()
![]() �@�@�@�@�@�@�@�@ ��w�Fsocial-oriented
activities
�@�@�@�@�@�@�@�@ ��w�Fsocial-oriented
activities
![]() �@�@�@�@�@�@�@�@ �j���Fefficiency-oriented
activities
�@�@�@�@�@�@�@�@ �j���Fefficiency-oriented
activities
�@�Љ�I���ݍ�p�̕����A�E��I���ݍ�p�������J�Ȍ��t���g���X���ɂ��邽�߁A�����ꂪ���J�ł���B
�AIde(1991)
�@���J�Șb�������ӂ�܂��������B�u�悢�}�i�[�v�ƂȂ�B(Goffman 1967, �АM�̂���n�ʂƂȂ����Ă������)
�E ��蒚�J�Ȍ���`���B
�E �l�̑㖼���̂��t�H�[�}���Ȏg�p�B
�E �i������j�y������悤�Ȑl�̑㖼��������邱�ƁB
�E �i�̂Ȃ��\��������邱�ƁB
�E �����h��(beautification honorifucs)���g�p���邱�ƁB
�BIde& Inoue(1992)
�@�@�@��ʂɁA�E��ł͏����͗͂��Ȃ��A�n�ʂ��Ⴂ���璚�J�Ȍ��t���g���Ƃ���Ă��邪�A���ׂ����ʁA�����n�ʂɂ��鏗���̕����A�Ⴂ�n�ʂ̏����������J�Ȍ��t���g�����Ƃ��킩�����B�n�ʂ�ۂ��Ȃ�����U�镑����\�����邽�߂ɁA���J���Ƃ��āA����Ƃ��Ďg�����Ƃ����������B
�Q�DThe indigenous way of looking at women�fs language
![]() ���{��̏����ꌤ���FKikuzawa
Toshio(1929 )�w�l�̌��t�̓����ɂ���
���{��̏����ꌤ���FKikuzawa
Toshio(1929 )�w�l�̌��t�̓����ɂ���
�E�j���̌��t�Ƃ̑Δ�ł͂Ȃ��A�u�ʑ��v�Ƃ��Ĉ����Ă���B�ʑ��Ƃ́A�n��E�E�ƁE�j���E�N��E�K���E����/�b�����t�̑��Ⴉ��N���錾�t�̈Ⴂ�̂��Ƃł���B����w�ł悭�g���镪�͕��@�B
�E �m�_�H�����ǂ̃O���[�v�ɑ����邩�ňقȂ錾�t���g�p���Ă����B
�R�DWomen�fs language in women�fs world
![]() �����̐��E�ɂ����鏗����F���[���ƗV���ꁨ����̏����͂����̌��t�͎g���Ă��Ȃ��B
�����̐��E�ɂ����鏗����F���[���ƗV���ꁨ����̏����͂����̌��t�͎g���Ă��Ȃ��B
![]() �W���I�F���t�W�A��l�̂̑㖼���Œj���̋�ʁB
�W���I�F���t�W�A��l�̂̑㖼���Œj���̋�ʁB
![]() �P�P���I�F�������Ђ炪�Ȃ����B�j���͊�����g�p�B�i��j��������
�P�P���I�F�������Ђ炪�Ȃ����B�j���͊�����g�p�B�i��j��������
![]() ���[���E�V���ꂪ���������ꂽ�̂͂��ꂼ��14���I�A17���I�̂��Ƃł���B
���[���E�V���ꂪ���������ꂽ�̂͂��ꂼ��14���I�A17���I�̂��Ƃł���B
�R�D�P���[��
![]() ���Ƃ��Ɛg���̍������������[�ɂȂ�B�c���̂��߂ɓ����B�K�������݂���B
���Ƃ��Ɛg���̍������������[�ɂȂ�B�c���̂��߂ɓ����B�K�������݂���B
![]() ���[�̎d���F�c���̎����A�c�q�̋���A�d�v�ȏ���m�点�邱�ƁA�ȂǁB
���[�̎d���F�c���̎����A�c�q�̋���A�d�v�ȏ���m�点�邱�ƁA�ȂǁB
![]() �V�c�ƋM���̋��n���I���݂����A�����͂ƂĂ��d�v�B
�V�c�ƋM���̋��n���I���݂����A�����͂ƂĂ��d�v�B
![]() ���[��8���I���瑶�݂��邪�A���[�������ꂽ�̂�14���I����B����͎����ŁA�M���̖v���A���̖u�����n�܂���������B
���[��8���I���瑶�݂��邪�A���[�������ꂽ�̂�14���I����B����͎����ŁA�M���̖v���A���̖u�����n�܂���������B
![]() ���[���́A(a)�V�c�ƁA�M���̋ꂵ�������������߁A(b)�M���̕n����������悤�Ȕ��b������邽�߁A�ɗp�����n�߂��B
���[���́A(a)�V�c�ƁA�M���̋ꂵ�������������߁A(b)�M���̕n����������悤�Ȕ��b������邽�߁A�ɗp�����n�߂��B
![]() ���[���́A�W�c���ł͎g��ꂽ���A�W�c�O�ɂ͗�������Ȃ��悤�ȈÍ��Ƃ��ċ@�\�����B
���[���́A�W�c���ł͎g��ꂽ���A�W�c�O�ɂ͗�������Ȃ��悤�ȈÍ��Ƃ��ċ@�\�����B
![]() ��b�I���ʂ�ς��A���C�ⓝ��͕ς��Ȃ��悤�Ȍ��������B�����b�ɑ����B
��b�I���ʂ�ς��A���C�ⓝ��͕ς��Ȃ��悤�Ȍ��������B�����b�ɑ����B
![]() ���[���̎�ނ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
���[���̎�ނ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�ŏ��̉��߂݂̂��g�p����B�i�������Ȃ��j
�A�Ō�̉��߂��Ȃ����A�ŏ��̉��߂��J��Ԃ��B�i�����������j
�B�����̓ǂݕ���ς���B�i����ˁ����߁j
�C�����Ɠ������h�ꉻ����B�i���݂��������A�����オ�遄�H�ׂ�j
�D����̌`�e�������B�i�����������ނ܂����Ɓj
![]() �����̋@�\�́A�P��̖��m�ȈӖ����B�����Ƃ������B���̂��߁A�O���̐l�ɂ͗����ł��Ȃ��悤�ɍ��ꂽ�B
�����̋@�\�́A�P��̖��m�ȈӖ����B�����Ƃ������B���̂��߁A�O���̐l�ɂ͗����ł��Ȃ��悤�ɍ��ꂽ�B
![]() �Ȃ������̌����邱�Ƃ��K�v�������̂��H
�Ȃ������̌����邱�Ƃ��K�v�������̂��H
�@�o�ϓI�n��������Ɍ���Ȃ����߁B�i�B��H�̕Ă��Ȃ��A�Ƃ͌����Ȃ��̂œǂݕ���ς����B�j
�A���ۂ͌��͂��������Ă��邪�A�O�ɂ͍��M�Ȉ炿���������邽�߁B�i�q�ǂ����g���悤�ȇA�̌������������B�j
![]() ���[���͂��炭����ƕ��m�̍ȁA���O�ւƍL�܂��Ă������B17���I�]�ˎ���̏����̃G�`�P�b�g�{�ɂ́A���[���̕\�������f���Ƃ��ċ������Ă���B
���[���͂��炭����ƕ��m�̍ȁA���O�ւƍL�܂��Ă������B17���I�]�ˎ���̏����̃G�`�P�b�g�{�ɂ́A���[���̕\�������f���Ƃ��ċ������Ă���B
![]() ����̓��{��ł́A���[���ٌ̈`�͒j���ɂ��g����B���[�������Ƃ����b�́A���{��̘b�҂ɂƂ��Ă��D�����A���J�ł���悤�Ɏv����B�i���݂��������X�`�A���߂�������j
����̓��{��ł́A���[���ٌ̈`�͒j���ɂ��g����B���[�������Ƃ����b�́A���{��̘b�҂ɂƂ��Ă��D�����A���J�ł���悤�Ɏv����B�i���݂��������X�`�A���߂�������j
�R�D�Q�V����
![]() 17���I����19���I�i�]�ˎ���ň��肵�Ă��鍠�j�ɂ����āA�V���ꂪ���܂ꂽ�B
17���I����19���I�i�]�ˎ���ň��肵�Ă��鍠�j�ɂ����āA�V���ꂪ���܂ꂽ�B
![]() ���͓��쏫�R�ƂɎx�z����A�����̍Œ��ł���A�����͑�O�������J�Ԃ������B�m�_�H���̐g�����B
���͓��쏫�R�ƂɎx�z����A�����̍Œ��ł���A�����͑�O�������J�Ԃ������B�m�_�H���̐g�����B
![]() �V���́A�o��⊿��̒m���A���y�A���x�ɒ����Ă��邱�Ƃ����҂���A���̑��h�����E�Ƃƌ��Ȃ���Ă����B
�V���́A�o��⊿��̒m���A���y�A���x�ɒ����Ă��邱�Ƃ����҂���A���̑��h�����E�Ƃƌ��Ȃ���Ă����B
![]() ���i���s�j�A��g�i���j�A�]�ˁi�����j�ŁA�قȂ�n���A�Љ�I�w�i�A���������l�X�Ƃ��𗬂ł���悤�ɂƋ��ʌ�Ƃ��č��ꂽ�B�V����̃A�N�Z���g�́A�V���̏o�g���B���̂ɂ����������B
���i���s�j�A��g�i���j�A�]�ˁi�����j�ŁA�قȂ�n���A�Љ�I�w�i�A���������l�X�Ƃ��𗬂ł���悤�ɂƋ��ʌ�Ƃ��č��ꂽ�B�V����̃A�N�Z���g�́A�V���̏o�g���B���̂ɂ����������B
![]() �V���̓Ɠ��̘b�����́A�������E��Y�ꂳ����悤�ȁA���y��]���̕��͋C�����o�����B
�V���̓Ɠ��̘b�����́A�������E��Y�ꂳ����悤�ȁA���y��]���̕��͋C�����o�����B
![]() ����w�I�����͈ȉ��̒ʂ�B
����w�I�����͈ȉ��̒ʂ�B
�@�������������ɂ����ƁB���̕ω��͗]���ƊE�f���Ă���B���̑��ݍ�p�I�ȍs���́A�Ӗ���ς����ɘb�ҁ\������̕��͋C�ɂ���ĕ\����ς�����Ƃ������_���������̂ŁA�ł��悭�g��ꂽ�B�i���ǂ݂Ȃ��遄���ǂ݂ɂȂ�j
�@�@�A�P�l�́A�Q�l�̂̌Ăѕ�������ꂽ���ƁB�i�킿����������A���������ʂ��j
![]() �V����͂������s��������j�A���ɂ͏��Ȃ��Ƃ������͂��ꂽ�B
�V����͂������s��������j�A���ɂ͏��Ȃ��Ƃ������͂��ꂽ�B
![]() �V���͋��{���x�������������̂ŁA���O�̒��ӂ������A�^�̓I�ł��������߁A�̕���Ɏg��ꂽ��A���O���܂˂��肷��悤�ɂȂ����B�ŏ��͖��O�̏����ɍL�܂�A�V����Ƃ��ẴX�e�[�^�X�͂Ȃ��Ȃ�A���̂����j���ɂ��g����悤�ɂȂ����B����ł͒j���A�����Ƃ��Ɏg�����t�ł���B
�V���͋��{���x�������������̂ŁA���O�̒��ӂ������A�^�̓I�ł��������߁A�̕���Ɏg��ꂽ��A���O���܂˂��肷��悤�ɂȂ����B�ŏ��͖��O�̏����ɍL�܂�A�V����Ƃ��ẴX�e�[�^�X�͂Ȃ��Ȃ�A���̂����j���ɂ��g����悤�ɂȂ����B����ł͒j���A�����Ƃ��Ɏg�����t�ł���B
�S�DThe impact on present-day women�fs language
![]() �ŏ��̏������8���I�ɖ��t�W�ŏo���B���̂Ƃ����珙�X�ɒj���A�����͈Ⴄ�����b���n�߂Ă����ƍl�����邪�A�傫�ȉe���͂Ȃ��B
�ŏ��̏������8���I�ɖ��t�W�ŏo���B���̂Ƃ����珙�X�ɒj���A�����͈Ⴄ�����b���n�߂Ă����ƍl�����邪�A�傫�ȉe���͂Ȃ��B
�S�D�PEstablishing women�fs language as a group language
![]() ���[���ƗV����͂Ƃ��ɃO���[�v�̓��ꐫ����������Ƃ��ċ@�\���Ă����B
���[���ƗV����͂Ƃ��ɃO���[�v�̓��ꐫ����������Ƃ��ċ@�\���Ă����B
![]() ������̐��E�ł́A�悭��b�͕ω����Ă����B�������t�O���g���ƁA�V�N��������ƐM�����Ă�������B�i�Ȃ����Ȃ��сF�͎̂�ɏ������g���Ă������A���ł͒j�����g���Ă���B���V���Ȍꂪ�K�v�B�u���Ȃ��v�������B���́u���v�͂Ȃ��ɑ��鑸�h�ł͂Ȃ��A������Ƃ��Ęb�҂̐U�镑���������\���Ƃ��ĉ�����ꂽ�B�j
������̐��E�ł́A�悭��b�͕ω����Ă����B�������t�O���g���ƁA�V�N��������ƐM�����Ă�������B�i�Ȃ����Ȃ��сF�͎̂�ɏ������g���Ă������A���ł͒j�����g���Ă���B���V���Ȍꂪ�K�v�B�u���Ȃ��v�������B���́u���v�͂Ȃ��ɑ��鑸�h�ł͂Ȃ��A������Ƃ��Ęb�҂̐U�镑���������\���Ƃ��ĉ�����ꂽ�B�j
![]() ���[����V����́A�ꌹ�I�ɂ͌���̏�����̒��ڂ̐�c�ł͂Ȃ����A���ɂ��g�p�i�̈Ⴂ�j�����߂ċL�^���ꂽ���̂ł���B
���[����V����́A�ꌹ�I�ɂ͌���̏�����̒��ڂ̐�c�ł͂Ȃ����A���ɂ��g�p�i�̈Ⴂ�j�����߂ċL�^���ꂽ���̂ł���B
�S�D�QIndexing group identity and molding the speaker�fs self
![]() ������͐E�ƓI�W�c�̓��ꐫ���͂���}�[�J�[�Ƃ��ċ@�\���Ă����B
������͐E�ƓI�W�c�̓��ꐫ���͂���}�[�J�[�Ƃ��ċ@�\���Ă����B
![]() ��������g�����Ƃɂ���āA(a)�W�c�̋����������A(b)�����͂����̏W�c�ɑ����Ă���ƌ��Ȃ��A(c)�W�c�ɂ����l�X�𒇊ԂƂ��Č`�Â����Ă����B
��������g�����Ƃɂ���āA(a)�W�c�̋����������A(b)�����͂����̏W�c�ɑ����Ă���ƌ��Ȃ��A(c)�W�c�ɂ����l�X�𒇊ԂƂ��Č`�Â����Ă����B
�S�D�RAdding valuable image
![]() ������̕��y�́A�l�X���ǂ̂��炢�m��I�ɑ����Ă������Ƃ����w�W�ɂȂ�Ɖ��߂��Ă��悢�B
������̕��y�́A�l�X���ǂ̂��炢�m��I�ɑ����Ă������Ƃ����w�W�ɂȂ�Ɖ��߂��Ă��悢�B
![]() ���Ƃ��A�u�H�ׂ�v�Ƃ�����b�̕ω�������B�����͌�����{��ł��g���Ă���B
���Ƃ��A�u�H�ׂ�v�Ƃ�����b�̕ω�������B�����͌�����{��ł��g���Ă���B
�@�H��
�A�H�ׂ�
�B���H�ׂɂȂ�i�h��\���j
�C�����オ��i���[���̌h��j
�D�H�ׂȂ���i�V����̌h��j
![]() �C��D�͂�苳�{������A�D���Ȍ�ł���Ƃ������Ƃ��܂�ł���B
�C��D�͂�苳�{������A�D���Ȍ�ł���Ƃ������Ƃ��܂�ł���B
�T�DConclusion
![]() ���{�̕����̃R�~���j�P�[�V�������A�قȂ鎞���E�W�c��ΏۂɁA����w�̎�@��p���ĕ��͂������̌����́A���̕����̌����ɂ��V���ȉ\�������邱�Ƃ������Ă���B
���{�̕����̃R�~���j�P�[�V�������A�قȂ鎞���E�W�c��ΏۂɁA����w�̎�@��p���ĕ��͂������̌����́A���̕����̌����ɂ��V���ȉ\�������邱�Ƃ������Ă���B
![]() ����ӂꂽ������ᖡ���Ȃ��Ŋw��Ɏ�����Ȃ��ق����悢�B������͒Ⴂ�n�ʁA�͂̂Ȃ��ƊW���Ă���Ɠ����ꂩ�˂Ȃ��B���̌����ł́A������̋@�\���w�E���A����܂Ō��Ȃ���Ă��Ȃ������悢�ʂ�����Ă���̂ŁA�V�������͕��@������������Ă���B
����ӂꂽ������ᖡ���Ȃ��Ŋw��Ɏ�����Ȃ��ق����悢�B������͒Ⴂ�n�ʁA�͂̂Ȃ��ƊW���Ă���Ɠ����ꂩ�˂Ȃ��B���̌����ł́A������̋@�\���w�E���A����܂Ō��Ȃ���Ă��Ȃ������悢�ʂ�����Ă���̂ŁA�V�������͕��@������������Ă���B
![]() �����̗��j�����鉿�l�́A���̏������̂̌���ɂȂ��炦�悤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ���B����猾�t�ɉ����N���������Ƃ������͂���@���A���{�l�����͑����̏W�c����ɑ����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���B���ہA�����̐l�������̏W�c�ɑ����Ă���Ƃ�����B
�����̗��j�����鉿�l�́A���̏������̂̌���ɂȂ��炦�悤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ���B����猾�t�ɉ����N���������Ƃ������͂���@���A���{�l�����͑����̏W�c����ɑ����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���B���ہA�����̐l�������̏W�c�ɑ����Ă���Ƃ�����B
![]() �����̏W�c���E�ƌ��L���Ă��āA���̎g�p�����Ԃ̂��邵�ł���Ƃ����l�����́A�V�����͂Ȃ��B
�����̏W�c���E�ƌ��L���Ă��āA���̎g�p�����Ԃ̂��邵�ł���Ƃ����l�����́A�V�����͂Ȃ��B
![]() ���{��ɂ����ẮA�j�����g�����A�����݂̂��g����Ƃ����P��͂Ȃ��B
���{��ɂ����ẮA�j�����g�����A�����݂̂��g����Ƃ����P��͂Ȃ��B
![]() �����̓��{�ꏗ���ꌤ���ł́A�j���ƑΏƂ����Ƃ��ɁA�����͗͂��Ȃ�����A������͏]���ɋN��������Ƃ��Ă��邪�A���̐V�����A�v���[�`�͏�����̍m��I�Ȗʂ���j���甭�����Ă���B������̋@�\���݂邱�Ƃɂ���āA������͏������g�̃Z���X��A�W�c�S�̂����߂�d�v�Ȗ��������邱�Ƃ��킩��B
�����̓��{�ꏗ���ꌤ���ł́A�j���ƑΏƂ����Ƃ��ɁA�����͗͂��Ȃ�����A������͏]���ɋN��������Ƃ��Ă��邪�A���̐V�����A�v���[�`�͏�����̍m��I�Ȗʂ���j���甭�����Ă���B������̋@�\���݂邱�Ƃɂ���āA������͏������g�̃Z���X��A�W�c�S�̂����߂�d�v�Ȗ��������邱�Ƃ��킩��B
![]() ����w�́A����ʓI�ȍŋ߂̌���g�s�b�N�̕��͂��Ă����B���̊T�O�͓��{�ꂾ���łȂ����̌���ɂ��L�p�ł��邾�낤�B
����w�́A����ʓI�ȍŋ߂̌���g�s�b�N�̕��͂��Ă����B���̊T�O�͓��{�ꂾ���łȂ����̌���ɂ��L�p�ł��邾�낤�B
Janet S. Shibamoto Smith
Gendered structures in Japanese
�P�DIntroduction
![]() ���{��b�҂͐��E��13��1000���l���݂���B�b�҂̓u���W����500���l�A�A�����J���O���ɂ��������邪�A�唼�͓��{�Řb����Ă���B
���{��b�҂͐��E��13��1000���l���݂���B�b�҂̓u���W����500���l�A�A�����J���O���ɂ��������邪�A�唼�͓��{�Řb����Ă���B
![]() ���{��̓A���^�C�ꑰ�Ƃ����Ă����邪�A�����ɂ͋N�����킩��Ȃ��Ǘ���������ł���B
���{��̓A���^�C�ꑰ�Ƃ����Ă����邪�A�����ɂ͋N�����킩��Ȃ��Ǘ���������ł���B
![]() ���{��̓���
���{��̓���
�E �ތ^�F�P�����SOV�^�B
�E ����F������̂��ƂɌ�u��������i�G�~�R���������j�B
���L�҂͏��L���ꂽ���̂��C�����i�A���\�����{�j�A�W���͑O����C������i�悭���F�B�j�B���̌`�ԑf�͎�ɐڔ�����������B
���\�������B����\���}�[�J�[�Ƃ��āA�u���v�u�́v������A�����͈ȉ��̂Ƃ���B
�u���v�F�s��/����������킷�B�i�Ԏq�����V�̌����R�����B�j
�u�́v�F�����`����B�i�Ԏq�����V�̌����R�����B/�@���V�̌����Ԏq���R�����B�j
�@�@�@�@�@�@�@�Ɖ��\���͕����ŕ\�����B�i�h��╶���̏����Ȃǁj
�@�@�@�@�@�@�@�ޕʎ���������B�S������w�I�ȓ����ɂ�蕪�ނ����B
�E ���C�F5�ꉹ�i/a e i o u/�j�A16�q��(/p t k b d g s z h r m n w j/)�B
�@�@�@�@�@�g�[������Ƃ����l������A�s�b�`�A�N�Z���g�̌n���Ƃ����l������B
�E ��b�F�u�a��v�u����v�u�O����v�B�������Ώۂ⌻�ۂ�����킷�̂ɂ���������������B
�E �������F�u�����v�u�Ђ炪�ȁv�u�J�^�J�i�v�������@�͐��ݓI�ɏ_��B
�E �����F�������݂��邪�A���ʌ�ŃR�~���j�P�[�V�������Ƃ��B
�E ������F���@�I�Ȑ��͑��݂��Ȃ����A���c��(1957)�͏�����ٕ̕ʂ͑��݂���Ǝ咣�B
�@�@�@�@�@�@Inoue(1996)�ɂ��ƁA�u�����ɂ���Ďg���錾��͏������L�̂ӂ�܂��A���܂�Ȃǂƌ��т��Ă���v�B
�@�@�@�@�@�@Shibatani(1990)�͉��C�̈Ⴂ�A��b�ⓝ��̈Ⴂ������Ǝ咣�B
�@�@�@�@�@�@�@����ɁA�����͊���̎g�p�͏��Ȃ��A���i�Ȍ��t��������J�ł���A�Ƃ��咣�����B
�Q�DGendered structures
![]() Weatherall(1998)�F�j���Ə����̌���̍��ق́u���ɉ����Ă���A��{�I�ŁA�T�^�I�v�ł���B
Weatherall(1998)�F�j���Ə����̌���̍��ق́u���ɉ����Ă���A��{�I�ŁA�T�^�I�v�ł���B
![]() Kitto(1989)�F���{����j���E����������čl����Љ�B�hgender reference�h
Kitto(1989)�F���{����j���E����������čl����Љ�B�hgender reference�h
�Q�D�P�����ɂ��Ęb���F��b�I�ȃo�C�A�X
![]() ��b�̃W�F���_�[�͓��{��ɂ����݂���B
��b�̃W�F���_�[�͓��{��ɂ����݂���B
![]() �u�l�ԁv�u�l�v�ȂǁA�[���Ɖ����ʂ̂Ȃ����t���B�������A�u�l�ԁv�u�l�v�͏��������Ă���Ƃ�������B
�u�l�ԁv�u�l�v�ȂǁA�[���Ɖ����ʂ̂Ȃ����t���B�������A�u�l�ԁv�u�l�v�͏��������Ă���Ƃ�������B
![]() Endo(1991)�F�����̒�`������B
Endo(1991)�F�����̒�`������B
|
|
�@�@�@�@�@�@�j |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
|
�A�z |
�����A���h�ȁA���_�A�ʖ� |
���ꂢ�ȁA�D���� |
|
|
�j�̎q |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎q |
|
�g�p�� |
�����Ɏq���ɂ����g���B |
��l�̏����ɂ��g���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����̒n�ʂȂ킹�A�Љ�I�ɒႢ�n�ʂɂƂǂ߂��Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B |
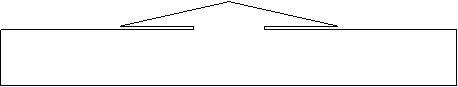 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̔�Ώ̐�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ł͌�����邪�A�����ɂ͂��܂��Ɏc���Ă���B
![]() Nurita(1993)�F�������w����̔�r
Nurita(1993)�F�������w����̔�r
�@�@�@�w�l�F�`���I�ȈӖ��������A���ʂɏd����u���Ȃ��B
�@�@�@���@�F�����I�Ȑ��̑��ʂ������B
�@�@�@�����F�C���h�E���[���b�p��̃W�F���_�[�̌ꂩ��h�������B�X�}�[�g�ł���Ƃ����܈ӂ����B
![]() Endo(1991)�F�j���E�����Ƃ�������
Endo(1991)�F�j���E�����Ƃ�������
�@�@�@�P�Ƃŗp�����镪�ɂ͑ΏƐ�������B������ɂȂ�ƑΏƐ����Ȃ��Ȃ�B�i�L�ҁ������L�ҁA�E���������E���j
�@�@�@�Ȃ��u�������v�Ƃ����ꂪ�����āA�u�j�����v�Ƃ�����͂Ȃ��̂��H
![]() ���t�Ə����l�����(1985)�F�����Ɋւ��錾�t�̃J�e�S���[�𖾂炩�ɂ���B
���t�Ə����l�����(1985)�F�����Ɋւ��錾�t�̃J�e�S���[�𖾂炩�ɂ���B
�@�@�@���n�F���������A�����A���� / �j�������q�A���N�A����i�j���̕\�������Ή����Ă���j
�@�@�@�����O�F�����E�j�����V���O�� / �j�����Ɛg / ����������c��i�����̌������������C���[�W�j
�@�@�@���I�ΏۂƂ��Č����関�������F��w�A���l�A���A���t�w�i�������w�����݂̂ɑ��݂���j
�@�@�@�����F��������w�A�� / �j������l�A�v�i�j���̕\�������Ή����Ă���j
�@�@�@�@�@�@�ق��ɁA���[�F�{���̏������w�����t������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɠ��F�����̍Ȃ��w���Ƃ��Ɏg��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������F���l�̍Ȃ��w���Ƃ��Ɏg��
�@�@�@�@�@�@ ���C�t�F�u�Ɠ��v�Ƃ����C���[�W�͂悭�Ȃ��̂ŁA����@���邽�߂Ɏg��
�E �������A�u�ꐫ���v�̂悤�ɁA�����̕����悢�C���[�W�����悤�Ȍ������B
�E ���j��A�������������̋�ʂ������́A�`���I�ȘJ���̌n��A�u�Ɓv�̌n�ɗR�����Ă���A�����̕]���������邽�߂̌�Ƃ���Ă���B
�E �����Ɋւ����́A�����̈ʒu���̕��͂f���Ă���A�����̒�`���ǂ̂悤�ɏ������ʒu�Â��Ă��邩�����邱�Ƃ��ł���B
�Q�D�Q�����̘b����
![]() ���c��(1957)�̂����u�^�̏�����v���x�[�X�ƂȂ��Ă���\���I�ȓ�����������B
���c��(1957)�̂����u�^�̏�����v���x�[�X�ƂȂ��Ă���\���I�ȓ�����������B
�Q�D�Q�D�P���C
![]() ������́A�j����荂���s�b�`�Řb�����B�i�����w��̐������������s�b�`�B�j
������́A�j����荂���s�b�`�Řb�����B�i�����w��̐������������s�b�`�B�j
![]() Shibamoto(1985)�F�ȉ��̂R�̓������B
Shibamoto(1985)�F�ȉ��̂R�̓������B
�@/i/�̍폜�i�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A/r/�̓����i�킩��Ȃ����킩��Ȃ��j�@
�Ba)�ꉹ�̒������i�悭�����̂恨��[�������̂�j�@b)�q���̑������i�ƂĂ����Ƃ��Ă��j
�����ۂɂ͏����Ɍ���ꂽ���̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B����Ȃ钲�����K�v�B
![]() �j���Ɍ�����A��d�ꉹ�̏k��̓T�^
�j���Ɍ�����A��d�ꉹ�̏k��̓T�^
�@/ai/��/eː/�i�ɂ������Ă��j�A/ae/��/eː/�i���܂������߂��j�B/oi/��/eː/ �i���������������j
�Q�D�Q�D�Q���Q��
![]() �j���F�Ȃ��A�����A����낤�A����
�j���F�Ȃ��A�����A����낤�A����
![]() �����F����A�܂��A�������
�����F����A�܂��A�������
�Q�D�Q�D�R�㖼��
![]() ���{��̑㖼���͖{���ɑ㖼�����H��No.�@�㖼���͈�ʓI�ɁA��b�Ƃ������͓����̂��́B���{��͂��̒�`�ɂ͓��Ă͂܂�ɂ����B
���{��̑㖼���͖{���ɑ㖼�����H��No.�@�㖼���͈�ʓI�ɁA��b�Ƃ������͓����̂��́B���{��͂��̒�`�ɂ͓��Ă͂܂�ɂ����B
![]() �㖼���Ƃ��Č��Ȃ��ƌ��߂邱�Ƃɂ��āA�ł͂���̓W�F���_�[��\�����H��Yes and No.�@
�㖼���Ƃ��Č��Ȃ��ƌ��߂邱�Ƃɂ��āA�ł͂���̓W�F���_�[��\�����H��Yes and No.�@
��l��
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�i |
|
|
|
|
�j�� |
�킽�����@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�@�@�@�@�@�@�@�@�� �i�����j�@�@�@�@�i�킵�j |
|
���� |
�킽�����@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������j�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������j |
�E Ide(1979a),Shibatani(1990)�F�u�l�v�͒j�̂݁B�t�H�[�}���x�͒��B
�E Uchida(1997)�F�j�\���̉�b�ł́u����v���g���B�u�l�v���g���Ă���ƎႢ�����͔F�����Ă���B�u�������v���u�킽���v�Ɏ���đ����Ă���B�t�H�[�}���Ȕw�i�ł����Ă��B
�E Martin(1975)�F�u�킵�v�͓c�ɂ̂���������A�͎m�A�싅�I�肪�g���B
�E Kanemaru(1997)�F�j���̎g�p����u�����v�́A�K���������������Ƃ��Ɏg����i��ɌR���Łj�B�����̎g�p����u���������v�͂܂�ŁA�u�������v�͒Ⴂ�K���̐l���g���B
�E Ide &Hori&Kawasaki(1986)�F�^����ꂽ�w�i�̃t�H�[�}���e�B�̕]���́A�w�i�ɂ���đ㖼���̑I�����j���ƁA�����łȂ������ł͈قȂ���̂ł���B
��l��
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�i |
|
|
|
|
�j�� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă߂��@�@�@�@���J |
|
���� |
���Ȃ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� |
Ø ��l�̂���l�̂��A�����K���̏����A�v�A���ꂼ��̃X�s�[�`�𒆐S�ɏW�߂����̂ł���B�ق��̒n���K���ɂ͗p�S���ׂ��B
Ø Yamaguchi(1991)�F�㖼���̌��B���C�n���̕����ɂ͑̌n���Ȃ��B
Ø Tajiri(1991)�F��B�̕����ׂ�B
�Q�D�Q�D�S�I����
![]() McGolin(1999)�F�j�������A���A���A�ȁA�� / ��������A�i�ȁj��
McGolin(1999)�F�j�������A���A���A�ȁA�� / ��������A�i�ȁj��
![]() Reynolds(1985)
Reynolds(1985)
|
|
|
��@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��/���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Ȃ́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@�@�@�@�@�@ |
�E�����͒f��I�łȂ��`�����g�p����B
![]()
|
�j���ɂ���Ďg���鏕�� |
�j���E�����Ɏg���鏕�� |
�����ɂ���Ďg���鏕�� |
|
��� |
�j�������� |
��� |
|
��Ȃ� |
�� |
�̂� |
|
�� |
���Ȃ� |
������ |
|
����� |
���� |
�Ȃ̂� |
|
����Ȃ� |
�j�������� |
��� |
|
�� |
��� |
�̂� |
|
�Ȃ� |
�� |
�� |
|
�� |
�� |
�Ȃ� |
|
���� |
�������j�� |
�̂� |
|
|
�Ȃ́H |
����� |
|
|
�� |
�́H |
|
|
�您 |
|
�E �u��v�u�́v�F80���ȏ���������g�p / �u���v�u���v�u�ȁv80���ȏ��j�����g�p
�E ![]() �u���v�c�����x���ł̒f��F�j�����ω��������Ă��邱�ƂƊW������B�@�W�F���_�[�ɂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u���v�c�����x���ł̒f��F�j�����ω��������Ă��邱�ƂƊW������B�@�W�F���_�[�ɂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�E �u�ˁv�F�j���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��\���I�p�^
�E �u���v�u���v�u��/�Ȃ��v�u��ȁv�u����ȁv�F������ۂ����́c�j�@�@�@�@�@�@�@�|���͂Ȃ��B
�E �u��v�u��ˁv�u���v�F�@�ׂȌ��́c��
�E ���ʂɂ�镶�������c�`���ƌ��т��Ă���B
�E Inoue(1994,96)�F�n��ƊK������Ɍ����B
�E Matsumoto(1996)�F�j���́i����́j�`�̋�ʂ͗��j�I�Ȑ[������z�肳���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ƃ��Ă݂Ȃ����I�����u�Ă悾��v�́A�������キ�炢���珗����̓���ƂȂ����B
�E Matsumoto(1996)�F�u����ˁv�c�ȑO�͒j���̏I�������������A���ł͒j�����҂��g�p����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����́A�������T�^�I�Ȏp����V�t�g�������ʂƂ�����B
�Q�D�Q�D�T�[���K��
![]() Shibatani(1990)�F�u�[���K���v�i������K���j��āB�I�����u��v�����Ɓu���v��������i���₾�恨�����j�͏�����݂̂̌��ۂł���Ƃ����B
Shibatani(1990)�F�u�[���K���v�i������K���j��āB�I�����u��v�����Ɓu���v��������i���₾�恨�����j�͏�����݂̂̌��ۂł���Ƃ����B
�Q�D�U�h��
![]() �����̉�b�p�^�[�����j�����u���J�v���ƌ����闝�R��������Ȃ��B
�����̉�b�p�^�[�����j�����u���J�v���ƌ����闝�R��������Ȃ��B
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���v�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ł��E�܂��v |
|||
|
���h�� |
�搶�� |
�������ɂȂ� |
�������ɂȂ�܂� |
|
�搶�� |
������� |
������܂� |
|
|
���� |
�F�B�� |
���� |
�����܂� |
|
������ |
�킽������ |
���������� |
���������܂� |
|
�i�搶�̂��߂Ɂj |
�i�������������j |
�������������܂� |
|
![]() �h��Ɋւ��āA�\���I�Ȓj���̋�ʂ͂Ȃ������B�������A����̓W�F���_�[�ɂ��\�����ɈႢ������Ƃ���������B
�h��Ɋւ��āA�\���I�Ȓj���̋�ʂ͂Ȃ������B�������A����̓W�F���_�[�ɂ��\�����ɈႢ������Ƃ���������B
�E Ide& Hori&
(a)�����ƒj���ł́A�����`�ԑf�̌h��̌`�ɂ��āA���ꂼ��Ⴄ���l�ς������Ă���B�����͑̌n�I�ɁA�������̌`�Ɋւ��āA�u���J�łȂ��v�Ɗ�����B�j���͓��Ɋ����Ă��Ȃ��B
(b)�j��������������̑���ɑ��āu�ǂ����J�ł��邩�v���l���Ă��邪�A�����̕��͂�蒚�J�����K�v�ł���ƍl���Ă���B
�i���_�j�j���Ə����ł͌h��̎g�������Ⴄ�B�j���͊K����u��/�O�v�ɋC�����Ă��邪�A�����͋��{�⏗���炵�����ӎ����Čh����g���Ă���B
�E �j���Ə����ł́A�W�F���_�[�Ɋ�Â����J���̈Ⴂ�́A���͎Љ�I�]���ƈꏏ�ɂȂ��āA�Ӗ��̈Ⴂ��̌n�I�ɍ��o���Ă���B
![]() ���߂Ɨv��
���߂Ɨv��
�j���Fa) �N����b) �������܂�c) ������d) �N�����̂��@e) �����N��������
�����Fa) �N����b) �N�������傤����
�R�D�P�[�X�X�^�f�B
![]() ���� ��s�u���d���v[1]�̎�l���A
���� ��s�u���d���v[1]�̎�l���A
![]() �ȉ���������B(I:�s�q�AN:�i���[�V����)
�ȉ���������B(I:�s�q�AN:�i���[�V����)
�i�X�jI)�@�킠�B���Ă��B�@N)�@�����������\�������������B
�i�P�O�j�@I) ����ȏ�S���Ɉ������ƌ���Ȃ��ł�B���܂���A�킵���B
N)�@�Ƃ��ł��Ȃ��^��ł��������j�̂悤���������B
�i�P�P�j I) ������K�a�@�͊��̎v�f�Ō����Ȃɒ��ߏグ���ăA�b�v�A�b�v���Ă������Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@���܂��犔�匠�̍s�g�Ȃ�ėI���Ȃ��ƌ����Ă����Ȃ���ˁB
�@�@�@�@�@�@�����炤���ƃg�b�v����s����̘b��˂��ς˂��Ǝv����B
N)
���������j���t�Ə����t�����������ɁA���R�̌�����˂������悤�Ɍ������B
�i�P�Q�j�@I)�@���邩�Ȃ����A�����T�d�ɍl���Ă�����炳�B
B�|JAPAN��D�S�ݓX�����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��`���͂Ȃ���ˁB�����ł���B
N)
�������͏������A�����ނ��o���ɁA�j���t������������ׂ�n�߂��B
�i�P�R�j I)�@�������Ă킩��Ȃ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�܂��В��ɉ�Ă��Ȃ����A�����햱��J�����̂͂ǂ��������܂��Ă��Ȃ������B
�@�@�@�@�@N) �������́D�D�D���\�Ȍ����Ō������B
![]() �������A��ɂ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�v�A���q�A�e�Ƃ͏����̂悤�ɘb���B
�������A��ɂ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�v�A���q�A�e�Ƃ͏����̂悤�ɘb���B
�i�P�S�j I)�@���������Ȃ́B
�@�@�@�@�@�@�@����ƁA�В����̊܂݂܂ł��鍇�ӂ��Ă킯�ˁB
N)
�D�D�D���t�������T�����ł������B
�i�P�T�j�@I) �����A���Ⴉ�����ł��B
�@�@�@�@�@�@���̂���A�������܂����X�Ƃ��Ă��܂����B�@�@�@�@�@
N)
���Ǐ]�܂����Ȃ������̌��t�ɁA�K���Y�͑傰���ɏ����B
�i�P�U�j�@I)�@���ׂ������m�������̂�������܂���B
N)
���������T���߂��������B
�S. The feminist debate
![]() Tanaka(1995)�F1970-80�N��́u�V�v�t�F�~�j�X�g�̓����������Ă���B����́A�u���̎��R�v��ڎw���āA�������ʂ��hhack through�h���邽�߂Ɉӎ������߂悤�Ƃ�����̂������B
Tanaka(1995)�F1970-80�N��́u�V�v�t�F�~�j�X�g�̓����������Ă���B����́A�u���̎��R�v��ڎw���āA�������ʂ��hhack through�h���邽�߂Ɉӎ������߂悤�Ƃ�����̂������B
![]() �����̕ω��́A������̋K�͂�ς����B�j���I�ȃp�^�[�����g������A�����I�Ȍ���g�p�������肷��悤�ɂȂ����B
�����̕ω��́A������̋K�͂�ς����B�j���I�ȃp�^�[�����g������A�����I�Ȍ���g�p�������肷��悤�ɂȂ����B
![]() ���{��f�B�A�́A���������Ɏg��ꂽ�悭�Ȃ����t��r������悤�ɂȂ����B�i�u�X�A����c��A�K����A�I�[���h�~�X�j
���{��f�B�A�́A���������Ɏg��ꂽ�悭�Ȃ����t��r������悤�ɂȂ����B�i�u�X�A����c��A�K����A�I�[���h�~�X�j
![]() ����Ƃ͏�������邪�A���͕v�w�ʐ��̋c�_������Ă���B�i�^���h�F��������L�����A�𑱂����� / ���Δh�F�ƒ�̕�����j
����Ƃ͏�������邪�A���͕v�w�ʐ��̋c�_������Ă���B�i�^���h�F��������L�����A�𑱂����� / ���Δh�F�ƒ�̕�����j
�T�Dconclusion
![]() ���{��ɂ́A���@�I�ɂ̓W�F���_�[�̃J�e�S���[�͂Ȃ����A�Љ�I�ɂ͂���B
���{��ɂ́A���@�I�ɂ̓W�F���_�[�̃J�e�S���[�͂Ȃ����A�Љ�I�ɂ͂���B
![]() ��������\����������̕����̂Ƃ��ẮA19���I�㔼��20���I�ɂȂ��Ē�`�����悤�ɂȂ����B
��������\����������̕����̂Ƃ��ẮA19���I�㔼��20���I�ɂȂ��Ē�`�����悤�ɂȂ����B
![]() ���{��ɂ́A����������������Ƙb�����肷��̂ɁA�l�X�Ȍ�����������B
���{��ɂ́A����������������Ƙb�����肷��̂ɁA�l�X�Ȍ�����������B
![]() �����ƒj���̐����������_��ŕω��̂���21���I�ɂ́A�W�F���_�[�̌��t�́u��������������֖@�v�̒��S�I�ȗv�f�ł��葱���邩������Ȃ��B
�����ƒj���̐����������_��ŕω��̂���21���I�ɂ́A�W�F���_�[�̌��t�́u��������������֖@�v�̒��S�I�ȗv�f�ł��葱���邩������Ȃ��B